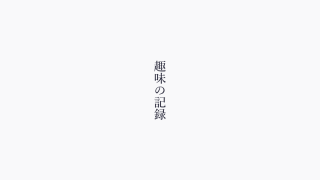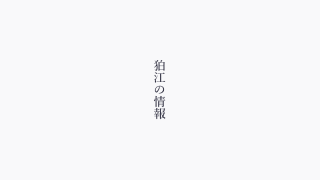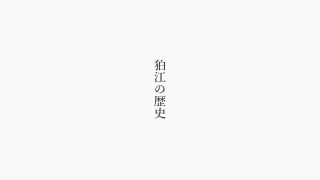竹内敏晴『思想する「からだ」』
 竹内敏晴『思想する「からだ」』
竹内敏晴『思想する「からだ」』
あるとき、朗読をする機会があったのだが、朗読は、「歌う」ことと比較すると決して難しいことではない、という先入観があった。
朗読する、声に出して読む、というのは、歌と違って生まれつきの障害を抱えていない限り、「習得する」というよりも、気づいたときには当然の能力として持っているものだ。
だから、そこに技術や能力の必要性を感じることはあまりなく、ただ普通に自分の地声で読めばいいのだろう、と思っていた。
しかし、その「地声」ということが、実はそんなに単純なものではないのだと、演出家の竹内敏晴さんの『思想する「からだ」』を読んで改めて考えさせられた。
竹内敏晴さんは、生後すぐに難聴になり、10代の半ば頃から徐々に聴力が回復していった、という体験を持っている。
そのため、「声」というものを、まるで僕たちがギターを覚えるように、後天的に習得していく必要があった。
そうして「声」を身につけていく過程で竹内さんが分かったことがある。
それは、言葉というのは、まず「声」だということ。
そして、その「声」とは、「からだ」を使った「全身の運動」であり、「呼びかけ」である、ということだった。
一方で、そのように相手に届け、伝える「良い声」「本当の声」を出すことができる人が少ない、ということも竹内さんは痛感する。
多くの人が「声」を持っていない理由として、一つは、「からだ」が常に固く、リラックスすることを知らないこと。
もう一つは、「違う誰かになろうとしている」ということを竹内さんは挙げる。
たとえば、女性店員の接客時の甲高い声は、媚びた、嫌われたくない、という思いが先行したような、言ってみれば「仮面」をかぶった声である。
メイクをした「声」を出しているということは、(声は全身運動なので)そういう「からだ」の使い方を、常にしているということでもある。
こうした「からだ」の使い方は、癖になる。
そして、無意識のうちに、日々の生活でも、接客の「声」を使うようになる。
それは、もはや自分の心からの「声」ではなく、借り物の声であり、そのため本当の気持ちを伝えたいときにさえ、自分の「声」が出せなくなるのだ。
多かれ少なかれ、僕たちは大人になるにつれて、自分の「声」を見失い、誰かの「声」になろうとする。
赤ん坊の泣き声のような、「この声が届かなければ、わたしは死んでしまう」という切迫した声が出せなくなる。
朗読や日常生活で、重みのある「良い声」、説得力のある語り方をするためには、その「声」の出し方、「からだ」の使い方を思い出す必要があるのだ。
声は、重要である。
それはカラオケの場だけではない。恋愛や就職活動の面接における「口下手」「話下手」の克服においても、声は他者との関係性を築くコミュニケーションの基本となる。
歌であれば、精一杯に美しく着飾る「良い声」が求められることもあるかもしれない。
しかし、日々のコミュニケーションの際の「良い声」は、むしろ「曝け出す」ことが大切になってくる。
そのことについて竹内さんは教えてくれる。
コミュニケーション力を向上させる方法や、どもりの悩みを克服する方法、口下手、話下手な自分を変える方法を知りたい人は、種々のハウツー本よりも、まず、この「声」と、「良い声」の出せる「からだ」の使い方について考えることが、結果的には近道になるかもしれない。
軽い声で言葉数ばかり増えるよりも、説得力と安心感のある「良い声」で一言、「わかった」と頷く方が、ずっと「コミュニケーション力がある」と言えるのではないだろうか。