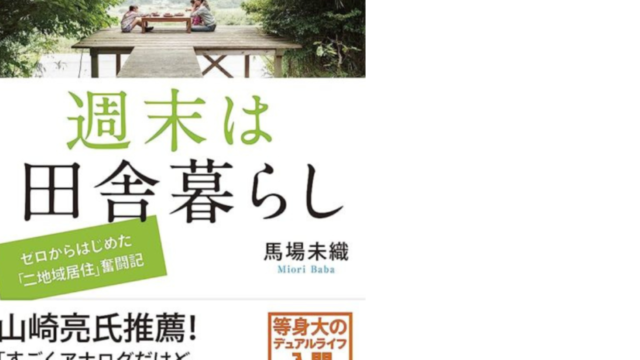人気の記事
-
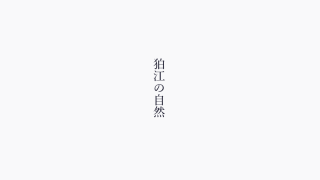
関東のトカイナカ〜都会に近い、または東京に通える田舎〜
13927 view -
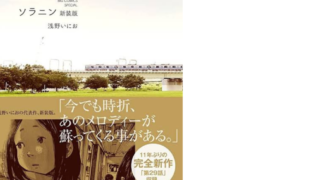
『ソラニン』の舞台
12176 view -
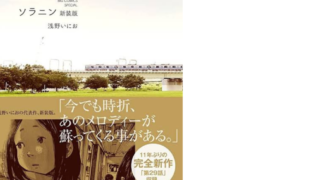
自殺か事故か、『ソラニン』種田の死の理由
9525 view -
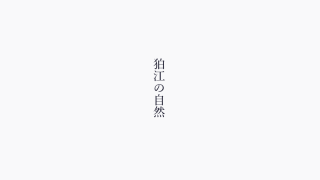
夏に「クークー、クックー」「ホーホー、ホッホー」と鳴く鳥の名前
8446 view -
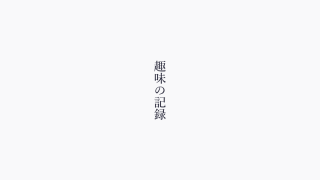
岩井俊二が語る、結婚と子供の存在
8108 view -
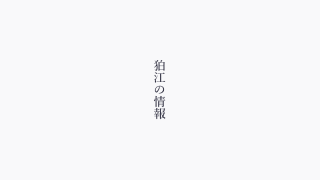
狛江の過去の多摩川氾濫(水害)とハザードマップ
8093 view -
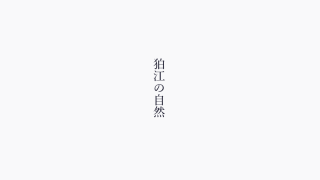
くちばしがオレンジの鳥
8044 view -

初夏の多摩川土手に咲く紫の花
7312 view -
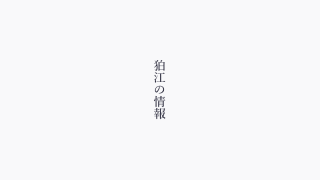
多摩川の蛇・マムシ出没注意の看板と、噛まれたときの対処法
7040 view -
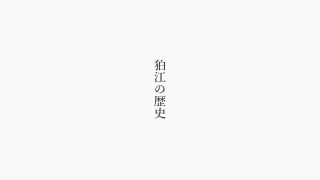
昔の小田急線の喜多見、狛江、和泉多摩川駅と多摩川
5488 view
最新記事
- 経堂で桜のお花見に最適な公園 2023年9月9日
- 狛江と和泉多摩川の住みやすさ 2020年8月17日
- 長い梅雨 2020年7月27日
- コロナと夏の夜の狛江の花火 2020年7月24日
- 夏頃の多摩川の土手に咲く白い花 2020年7月20日
カテゴリー
狛江から見た世田谷区たまがわ花火大会
撮影 Kei 2016年、夏