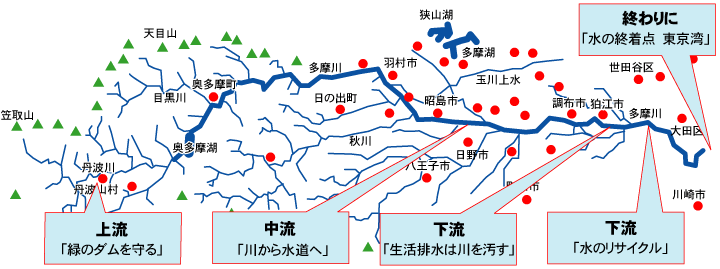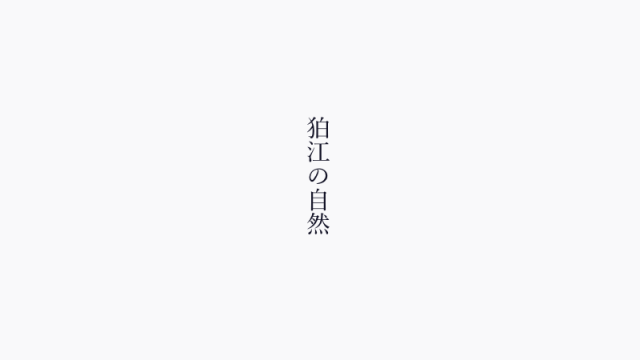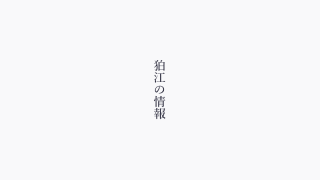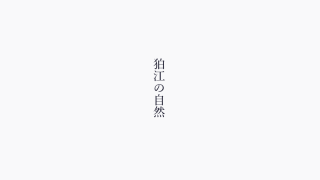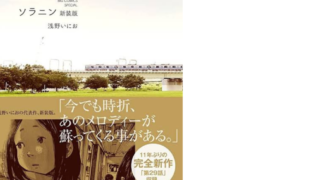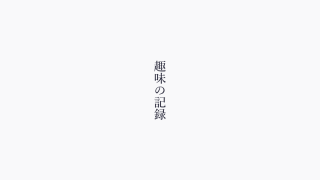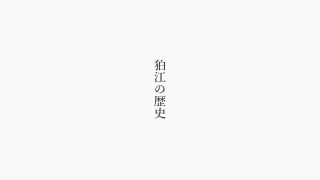東京都内でススキの名所、秋の多摩川
ススキとは
秋の風物詩と言えばススキ。ススキとはイネ科の植物で、秋の七草の一つとして、例年9〜10月頃に見頃を迎える。
ふわふわと涼しい風に揺れるススキの穂は、動物の尾っぽに似ていることに由来し、別名「尾花」と呼ばれることもある。
枯れススキのことを枯れ尾花と言い、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という有名な諺もある。
この言葉の出典は、江戸時代の国学者で俳人の横井也有の著書『鶉衣』のなかの俳句「化物の正体見たり枯れ尾花」が元と言われ、疑心暗鬼の状態では、枯れ尾花の揺れる様が、幽霊や化け物に錯覚してしまう、ということを意味する。
また、お月見のときにもススキを飾ることが多く、日本人にとって古くからススキは身近な植物として季節を彩ってきた。
ススキの名所「多摩川」
さて、そんなススキの名所の一つとして多摩川がある。
多摩川は、山梨と埼玉にまたがる笠取山を水源とし、東京都の西側、神奈川との県境の辺りを下りながら東京湾に向かって流れている。
僕が住んでいる狛江市も、狛江市内にある、小田急線の和泉多摩川駅近くを、多摩川が流れている。
和泉多摩川駅から歩いて数分で、秋の風に揺れるススキの穂と多摩川の景色と出会える。
多摩川とススキ
実際に立ってみると、風が心地よく、虫の鳴き声がりんりんと響き渡っている。