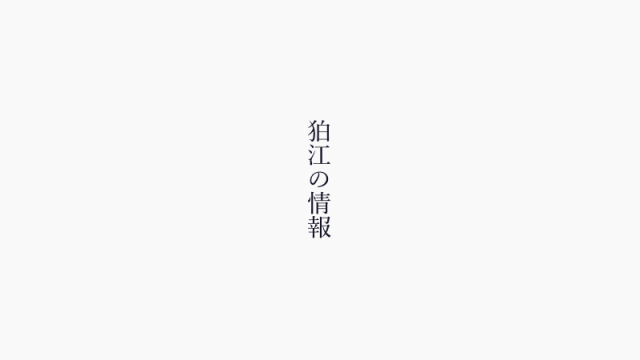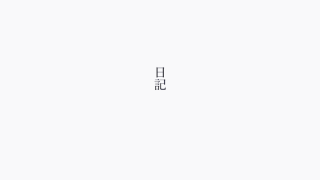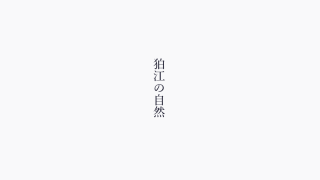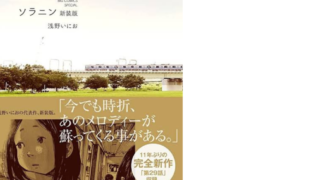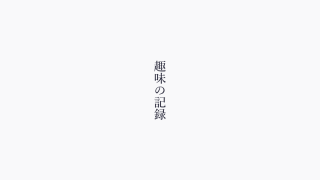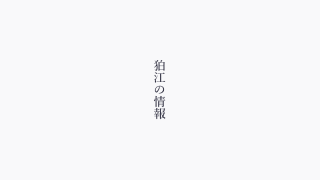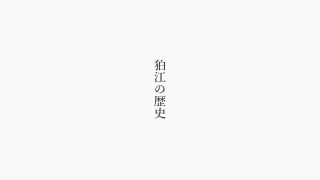多摩川の蛇・マムシ出没注意の看板と、噛まれたときの対処法
多摩川の蛇
狛江の多摩川近辺で、ときおり蛇を見ることがあった。蛇は、河川敷で見ることもあれば、川沿いから外れた人家の前の舗道をくねくねと素早く這っている姿を見たこともある。
見つけた瞬間は、怖いというよりも、単純に「お、蛇だ!」と驚くくらいだった。どうやら蛇は臆病らしく、僕が何度か会ったときも、こちらが驚くよりも先にさっさと物かげや草むらに逃げ隠れてしまった。
しばらくして、多摩川に蛇出没注意の看板が立った。
個人的な希望としては、こうした「出没注意」の看板については、まるで突然現れたり異常発生しているみたいな不安も生じるので、一言、「この辺りには昔からいるんですよ」と添えられているだけでもちょっと安心できるように思う。
また、最近では新しく、「蛇に注意」以外に、「マムシに注意」の張り紙も土手の看板に貼られるようになった。
もともと多摩川に生息する蛇としては、シマヘビやアオダイショウなど毒のないものだけでなく、毒ヘビであるマムシもいるようだ(以下「アウトドア趣味に関する総合情報サイト」参照)。

シマヘビ ナミヘビ科ナメラ属のヘビ。無毒。全長80-150cm。通常は淡黄色の体色に、4本の黒い縦縞模様が入るが、縞がまったくない個体もいる。全身が黒色に体色変異した黒化型は「カラスヘビ」とも呼ばれる。食性は幅広く、ネズミ、小鳥、トカゲ、カエル、ヘビ等を捕食する。あまり木に登らず、地表を素早く動く。

アオダイショウ ナミヘビ科 ナメラ属のヘビ。無毒。全長100-200cm。胴の直径は5cmほどになる。日本本土では最大のヘビで、南西諸島のサキシマスジオ、シュウダ、ホンハブに次ぐ大きさとなる。餌であるネズミの生息環境に対応し人家周辺でよく見られる。昼行性で、ネズミを追って家屋内に侵入することもある。

マムシ クサリヘビ科マムシ属のヘビ。毒蛇。全長45~80cm。全長に比して胴が太く短い。淡褐色の体色に、銭形模様といわれる独特の模様がある。水辺や草むら、土手、山地、森林などに生息している。毒は出血毒で、咬まれると激痛が襲い、患部が腫れ上がり内出血が拡大していく。毒性はハブの3倍も強く、咬傷被害での死亡例も一番多い。
蛇が生息していること自体は、自然が豊かな証拠でもあり、また彼らは基本的に臆病なので刺激しなければ勝手に逃げていくことも多いようだ。
マムシも、毒があるから攻撃的という印象を抱きがちだが、温和で臆病な性格と言われる。
「マムシ=猛毒=攻撃的=超危険」と連想する人は多いのではないでしょうか?毎年、マムシに噛まれたというニュースが聞かれますが、その多くはマムシの存在に気づかずに踏みつけてしまったときや、興味本位で捕まえよう(良い格好しよう)として噛まれるケースがほとんどです。マムシから攻撃してくることはありません。武器である猛毒も身を守るため、食べ物を得るために発達させたものなのです。
(中略)
マムシの性格は極めて温和で臆病な生きものです。逃げ場がないと尾を細かく振動させて威嚇してきますが、距離さえとっていれば攻撃してくることはありません。湿り気のある自然豊かな場所で、のんびりと暮らしています。マムシが見られる場所は多様性豊かな生きものたちの楽園なのです。
ただ、万が一毒を持った蛇に噛まれた場合(シマヘビなどは毒はないものの、噛むことはある。ただし、ほとんど重症化はしない)、適切な応急処置、対処法が必要となるので、一応調べたことをメモとして書き残しておこうと思う。
マムシに噛まれたときの対処法
マムシの見た目の特徴は、「頭が三角の形をしている」ということ。被害報告は夏場に集中している。
噛まれたあとの症状としては、次のようなものが挙げられる。
1、激痛、徐々に大きく張れ、皮下出血を起こし打撲傷のように紫色になる。
2、唇、歯茎、爪の下、局部に出血することがある。
3、ネフローゼ(筋肉組織が壊れること)、毒により白血球、赤血球が破壊され殺菌作用が低下するため化膿の危険が高くなる。
4、複視(ものが二重に見える)、発熱、悪寒、吐き気など。
5、放置しておくと死亡することがある。
出典 : マムシなど毒蛇に噛まれた場合の対処方法とは?
年間で1000〜3000人が被害に遭い、マムシに噛まれた被害者の0.3%(年間で10人ほど)が死亡まで至るケースもある。
噛まれた瞬間はチクっと刺さったような痛みで、最初はマムシに噛まれたことに気づかないことも多くある。
毒は、即座にまわるのではなく、数時間から一日をかけて徐々に全身に広がっていく。
毒のない蛇に噛まれたのか、マムシに噛まれたのかの見分け方として、噛まれた箇所に複数の点状の歯の跡があり、腫れがひどいようならマムシの可能性が高いそうだ。
いずれにせよ、尋常ではない「腫れ具合」というのが特徴だと言う。
噛まれたあとの対処法(応急処置)としては、調べると色々と意見が分かれていた。ただ、よほどのことがないかぎり死に至ることはなく、ゆっくりと体内をめぐるので、まずはパニックにならないこと、それから安静にすることが肝心、という点は共通していた。
また、水で洗い流したり、水分をとって利尿作用を高めること(毒を排泄するために)も大事なことのようだ。
口で吸い出したりタオルなどで縛って血流を止めることで毒の拡散を遅らせることについては、効果の有無や賛否が分かれていた。
あとは、病院に行くこと。
ただし、治療に関して、ある医師の声として、「血清は治療には必須ではない」という話もある。
医療処置として行う血清は、副作用や、アレルギーショックなどの危険性もあるが、もし万が一血清を打たずに患者が死亡してしまったら「必要な処置」を施さなかったとして裁判で負けるため、医師は「必要な処置」として血清を打つのだと言う(参照「ヘビに咬まれた、どうすりゃいいの?」)。
アレルギー体質の場合は、特にパニックになりすぎずに、その辺りにも注意を払う必要があるかもしれない。
確かに、マムシ自体は昔から存在した生き物であり、噛まれても病院に通わなかった人もいることを考えると、実際の致死率はもう少し低いのかもしれない。
昔の人たちは、どんな処置を行っていたのだろうか。
なんにせよ、異常発生ということでもなさそうなので、過度に恐れすぎることなく、気をつけながら過ごすことが大事なのかな、と思う。
ちなみに、狛江市のホームページには、昔の蛇との日常の記録が掲載されている。
屋根裏には必ずといっていいくらいヘビがすんでいた。しかも天井板など張られていなかったから、ときにはヘビが梁から座敷の真ん中にぶら下がっていたり、あるいはドサッと大きな音を立てて落ちてくることもあった。いかにヘビとの共同生活であっても、やはり気持ちのいいものではなかった。
だからヘビを見ると、「ヘビがいるわよ」と互いにささやき合ったが、ヘビを指差すことは決してなかった。ヘビを指差すと指先が腐ると言い伝えられ、恐れられていたし、また、ヘビは神様だとも言われていたので、決して殺すこともしなかった。